NORIS NATURE
LABO
NORIS PROFILE

所属:生態学研究センター 奥田研究室
役割①:研究生・TEAMコイ(水路担当)
②:炭火倶楽部・幹事
③:料理長補佐
氏名:藤 森 憲 臣
Contact me:nfuji@ecology.kyoto-u.ac.jp
学位:工学(修士)・名古屋大学
題目:取水量の大きい砂河川における付着藻類の一次生産に関する研究
NORIS NATURE
LABO
NORIS PROFILE

所属:生態学研究センター 奥田研究室
役割①:研究生・TEAMコイ(水路担当)
②:炭火倶楽部・幹事
③:料理長補佐
氏名:藤 森 憲 臣
Contact me:nfuji@ecology.kyoto-u.ac.jp
学位:工学(修士)・名古屋大学
題目:取水量の大きい砂河川における付着藻類の一次生産に関する研究
学歴:
熊本工業大学 工学部 土木工学科 工学(学士)
崇城大学(旧熊本工業大学)大学院 工学研究科 建設システム開発工学専攻
名古屋大学大学院 工学研究科 地圏環境工学専攻 工学(修士)
職歴:
(株)九州自然環境研究所 研究員
環境省中部地方環境事務所名古屋自然保護官事務所 自然保護官補佐
京都大学生態学研究センター
研究生
NORIS STUDY
在来淡水魚類の為の生息地ネットワーク形成技術に関する研究
~琵琶湖集水域におけるコイ科魚類の生息地評価とネットワーク構造の解析(水路担当)~
日本の河川や池、湖沼などにおいて「外来生物」が蔓延る現状は、 周知の通りです。そして、これが元来日本に生息する生物へ悪影響を及ぼしていることは、国により法整備がなされたり、またマスメディアに多々取り上げられ報道されていることからも、きっとご存知のことでしょう。
周知の通りです。そして、これが元来日本に生息する生物へ悪影響を及ぼしていることは、国により法整備がなされたり、またマスメディアに多々取り上げられ報道されていることからも、きっとご存知のことでしょう。
ここで言う「悪影響」には、様々な形態(外来生物の増大、それに伴う在来生物の減少、絶滅など)があり、その要因も多様に挙げられますが、本研究ではその要因の一つとして考えられる戦後からこれまでの「単調な水域空間の創造」を問題視しています。
 各在来生物にとって適した生息環境を維持していくことが、日本元来の「生物多様性の保全」を目指す上で非常に重要な課題です。
各在来生物にとって適した生息環境を維持していくことが、日本元来の「生物多様性の保全」を目指す上で非常に重要な課題です。
言い換えればこれは、「各生物種のイベント(繁殖や成長)を考えたとき、その成長段階(ステージ)に応じた生息環境及び微環境を保全することが必要である」ということです。
琵琶湖の場合、古くから本湖や内湖、用排水路、耕作地(水田)との密接な繋がりがあり、この繋がりが絶たれることで「個体数をこれまでに減少させている、これから減少させていく可能性」のある生物種がいることも近年分かってきています。
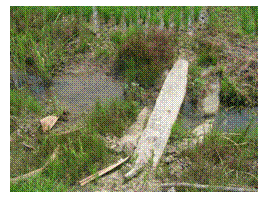 琵琶湖での水域ネットワーク構造の現状も危惧している通りであり、圃場整備においては「90%以上が終了している」と報告がされています。ですから用排水路と耕作地の間では、耕作地から用排水路へ落水する一方的な繋がりしか見られません。
琵琶湖での水域ネットワーク構造の現状も危惧している通りであり、圃場整備においては「90%以上が終了している」と報告がされています。ですから用排水路と耕作地の間では、耕作地から用排水路へ落水する一方的な繋がりしか見られません。
先にも述べたように、「単調な水域空間の創造(圃場整備や護岸、堰堤などの河川内構造物を含み)」は在来生物の生息適地の減少、種の保存の負荷に大きく影響していることは否めません。
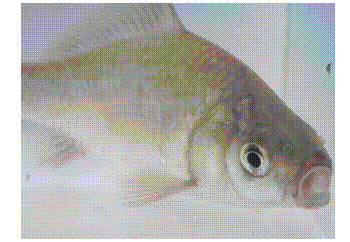 本研究では今後「琵琶湖集水域におけるコイ科魚類の生息地評価とネットワーク構造の解析」と題し、調査対象には用排水路と耕作地(水田)を中心として位置づけ、コイ科魚類の成長段階別好適生息環境と利用ネットワーク構造の把握・解明を
本研究では今後「琵琶湖集水域におけるコイ科魚類の生息地評価とネットワーク構造の解析」と題し、調査対象には用排水路と耕作地(水田)を中心として位置づけ、コイ科魚類の成長段階別好適生息環境と利用ネットワーク構造の把握・解明を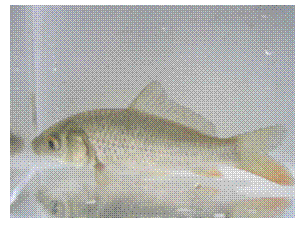 目的に今後も調査を行っていきます。
目的に今後も調査を行っていきます。