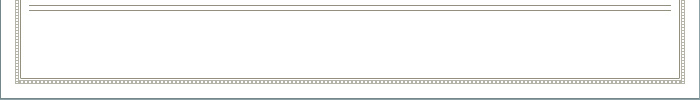遠藤千尋(京都大学生態学研究センター・’08在籍)


遠藤千尋(京都大学生態学研究センター・’08在籍)


生物群集のなりたちや保全を考えるときに、個々の生物の生息場所(ハビタット)を丁寧に明らかにし、把握することは非常に重要だと考え、空間や場所にこだわった研究をしたいと思っています。とくに、動物が構造物をつくることにより環境を改変する作用が、生物群集の形成にどのような影響を及ぼすのかに興味をもっています。また、外部につくった構造物を介して、物質の流れを変えたり、種内コミュニケーションするという、その情報のやりとりの方法にも興味があります。
これまでは地中に巣穴をつくるケラ(Gryllotalpa orientalis)の生活史と翅型二型の関係や巣穴構造とその空間利用などについて調べてきました(論文1、2)。今後は、翅型二型の地域変異と巣穴を介した音声コミュニケーションについて調べていく予定です。また、オーストラリアでオオニワシドリ(Chlamydera nuchalis)のあずまやをめぐるオスのdisplayと性選択についても調べ始めています。
今年は、アキアカネの減少原因のひとつとして、ウスバキトンボとの種間関係に注目した野外操作実験を行い、ヤゴ期の捕食のインパクトを明らかにする予定です。アキアカネは卵で越冬し5月頃ふ化します。ウスバキトンボは8月頃に南から飛来するトンボなのですが、温暖化による影響か、4月下旬頃から飛来し産卵する個体が増加しているようです。本来であわないはずのヤゴどうしが同じ水系に同居することになったときに、何がおこるのかを調べていく予定です。
学術論文
1.Endo, C. (2006) Seasonal wing dimorphism and life cycle of the mole cricket Gryllotalpa orientalis (Orthoptera: Gryllotalpidae). European Journal of Entomology, 103: 743-750.
2.Endo, C. (2007) The underground life of the oriental mole cricket: an analysis of burrow morphology. Journal of Zoology, 273: 414-420.
3.遠藤(2003)地下生活をおくる昆虫、ケラの巣穴の形とつかいみち. 昆虫発見2号:10-15 青葉出版.

研究内容

ケラの写真