A. 脱窒菌同位体比測定法ワークショップ2025
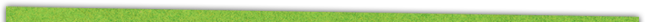


1.目的および内容
近年EA-IRMSの1/250の試料量で硝酸イオンの窒素、そして酸素同位体比を測定することができる「脱窒菌法」が開発され、世界中の最先端のラボにて利用が始まっている。しかし、この方法は脱窒菌の取り扱い、硝酸イオンからN2Oガスへ変換するサンプルの処理法、そして生データの補正など様々な点でEA-IRMSによる測定と比較して高度な知識が必要であり、一般的になるにはまだまだ時間がかかると見られている。
実際の測定は通常1週間を1サイクルとするが、本ワークショップでは、1サイクルの中で最も重要な硝酸イオンのN2Oガスへの変換に特化して実習を行う。同時に脱窒菌法の利用において散見される問題点についての講義を行う。まずは小規模で上級者を対象として、ワークショップを行い、今後の共同利用へつなげることを目的として開催する。
過去の様子はこちらをご参照ください。
https://www.ecology.kyoto-u.ac.jp/activities/publish/no0153.pdf(p8、2023年度)
https://www.ecology.kyoto-u.ac.jp/activities/publish/no0155.pdf(p7、2024年度)
参加カテゴリ (A,Bの2通りの申し込みパターン)
A .参加者ご自身の持ち込みサンプル5-10点程度あり
B .持ち込みサンプルなし
#今回持ち込み測定が可能な試料は硝酸イオン (NO3-) 濃度で3 micromole - N / L 以上のもので、事前に濃度がわかっているもののみです。
ワークショップ中に濃度測定は実施しません。実際の測定は7月頃を予定しております。
#トレーサーレベルの同位体は持ち込み不可です。
#通常、微量溶存有機物などは湿式酸化にて硝酸イオンに変換後、N2Oへ脱窒菌により変換します。このような測定についても詳細を講義予定このような試料について、測定のための前処理などを実施したい場合は、別途お問い合わせください。
2.担当スタッフ
木庭啓介(京都大学生態学研究センタ−)ほか
3.開催地
京都大学生態学研究センター(滋賀県大津市)
4.期間
2025年5月9日(金)13:00-15:00 zoom
脱窒菌法の基礎講義、作業動画など
5月12日(月) 9:00-17:00 @生態学研究センター
特殊脱窒菌前培養
5月13日(火)9:00-17:00 @生態学研究センター
脱窒菌へのサンプル導入、培養
5月14日(水)9:00-17:00 @生態学研究センター
脱窒活性停止処理
講義および質問
実際のデータの洗い方(検量線、、ブランク、量依存など)
応用について(NO3-以外の測定など)
5.受講定員
最大 3名程度(応募者が多数の場合には応募書類の志望動機にて判断します)
6.所要経費
受講費は不要。
ただし、資料のダウンロード、印刷、遠隔授業にかかる通信費は各自負担。
交通費、宿泊費、昼食代等は各自負担。
7.受講条件
脱窒菌法に興味がある研究者(学部生、院生可)。
同位体研究にある程度のなじみがあり、基礎的な知識を有している中上級者。
すでに安定同位体の基礎を理解している方対象です。
すべての日程に参加できる方。
学生(院生)は「学生教育研究災害障害保険」等に必ず加入し、指導教員に参加の承諾をえること。
8.応募方法および締め切り 2025年4月28日(水)9:00 締め切り
Googleフォームより申込ください。
9.受講者連絡先について
受講者への詳細な案内はe-mail にて行います。受講が決定した後、確実に連絡のとれるe-mail アドレスをお知らせください。また、携帯電話等でPC メールからの受信を制限している場合、kyoto-u.ac.jpからのe-mail を受信できるよう設定変更をお願いします。
尚、個別に受付完了の返信はしておりません。受講の可否の連絡を4月30日(水)以降に送信いたします。
1)脱窒菌法による微量溶存窒素化合物同位体比測定の基礎的原理についての講義
2)実際の脱窒菌を用いたサンプル前処理
3)前処理を行ったサンプルを用いた、安定同位体比質量分析計による測定
4)得られる生データの補正法についての講義と実習
5)海水、低濃度試料といった特殊試料への対応法の解説
希望者 は 5-10点/人 測定希望サンプル持ち込み可(トレーサー不可)
ただし、ワークショップでは前処理のみを行い、実際の測定は7月頃を予定しています。(後日データ送信します)
